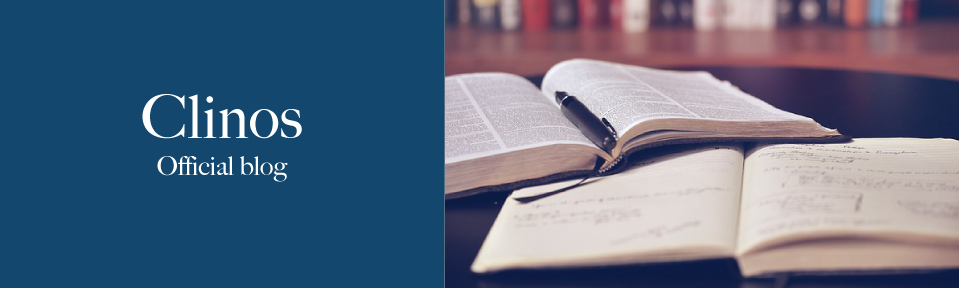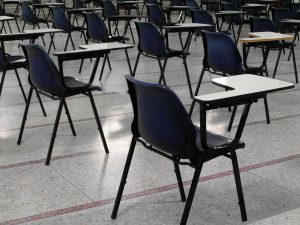【CORE Reference Newsとは】
治験総括報告書(CSR)のユーザーマニュアル『CORE Reference』を作成・公開している欧米のメディカルライターらから成るCORE Reference Teamが、無料配信しているニュースレター(英語)。メディカルライティングなどに役立つ医薬業界情報を欧米・アジアなどから集めて月1~2回配信。
※本ブログ記事は、クリノスがCORE Reference Teamの許諾を得て参考用として日本語に翻訳したものです。正確な内容や解釈は英語原文と各ニュース中のリンク先でご確認下さい。本ブログ記事の無断転載・転用は堅く禁止いたします。
【略語リスト】(アルファベット順)
- CDER:Center for Drug Evaluation and Research(米国医薬品評価研究センター)
- CIOMS:Council for International Organizations of Medical Sciences(国際医学団体協議会)
- CTIS:Clinical Trials Information System(臨床試験情報システム)
- CTR:Clinical Trials Regulation(臨床試験規則)
- EMA:European Medicines Agency(欧州医薬品庁)
- EU/EEA:European Union/European Economic Area(欧州連合/欧州経済領域)
- EudraCT:European Union Drug Regulating Authorities Clinical Trials
- FDA:Food and Drug Administration(米国食品医薬品局)
- HMA:Heads of Medicines Agencies(欧州医薬品規制当局首脳会議)
- ICH:International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use(医薬品規制調和国際会議)
- MHRA:Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency(英国医薬品医療製品規制庁)
- RWD:real-world data(リアルワールドデータ)
- RWE:real-world evidence(リアルワールドエビデンス)
1. CORE Reference Teamからのお知らせ
欧州メディカルライター協会(EMWA)の第57回総会が、2024年5月7~11日にスペインのバレンシアで開催されます。「EMWAシンポジウム・デー」である5月9日(木)の午前9:00~10:30に、CORE Reference Teamは対面式の無料オープンセッションを開催します。シンポジウムに参加登録済みの場合、同時にCORE Refenceのセッションに参加登録することはできませんが、当日セッション会場にお越し頂ければ、登録なしでご参加頂けます。なお、参加予定人数を把握するため、参加希望のご意向を事前にemwaconference@emwa.orgまでお知らせ頂けると幸いです。本セッションでは下記についてご説明する予定です。
- 臨床試験データ開示に対応した治験総括報告書(CSR)の作成における『CORE Reference』の価値と、CPD(Continuous Professional Development:継続的専門能力開発)のリソース
- EMA Policy 0070(臨床試験データ公開)試験結果提出の現実:計画したタイムラインと実際のタイムラインの比較など
- EMA Policy 0070(臨床試験データ公開)の再開:Anonymisation Report(匿名化報告書)テンプレートと完成の洞察
- 医療機器に関するCPD:医療機器と医薬品の融合など
- CORE Reference 2023年利用調査結果の概要
- 最新情報:改正CTIS透明性規則と新たなCTISウェブサイトの2024年6月開始や、医薬品販売承認申請(MAA)書類中の個人情報(PPD)と商業機密情報(CCI)に関する新ガイダンス案など
2. EU CTRとCTIS
2.1 EMAは「Revised CTIS transparency rules, historical trials and interim period: Quick Guide for Users」(改正CTIS透明性規則、過去の臨床試験、暫定期間: ユーザー向けクイックガイド)を更新しました。以下の3つのセクションが新たに追加されています。
- Historical trials(CTISの新公式サイト公開前にCTISに提出された臨床試験)
- Interim period approach(CTISの新公式サイト公開までの暫定措置)
- Revised CTIS transparency rules: useful material(改正CTIS透明性規則の関連資料)
2.2 2024年3月25日にEMAが開催した「Clinical Trials Information System Webinar: Last Year of Transition」(CTISウェビナー:移行最後の年)の録画ビデオが公開されました。
2.3 EMAは2024年4月24日15:30~17:00(中央ヨーロッパ夏時間)に、CTISショート説明会「alternate Investigational Medicinal Product Dossier – Quality (IMPD-Q) and new guidance on Auxiliary Medicinal Products (AxMP)」(代替治験薬書類–品質(IMPD-Q)および補助医薬品(AxMP)に関する新ガイダンス)を開催します。参加者はSlido経由でコード「#bt24apr」を使用して、4月17日まで事前の質問を提出できます。
2.4 EMAは、新たなCTISに対応する治験依頼者の準備をサポートするため、オンライン研修プログラム「CTIS sponsor end user training programme」(CTIS治験依頼者エンドユーザー研修プログラム)をユーザーに提供しています。次回の研修は2024年6月に開催予定で、参加申込の受付がこちらで始まっています。
2.5 2024年4月11日、欧州委員会の公式サイトの「Newsroom」ページは次のように報じました。「改正CTIS透明性規則は2024年6月18日に発効し、それに伴ってCTISウェブサイトの新バージョンが開設されます。改正CTIS透明性規則は、情報の透明性と商業上の機密情報(CCI)の保護とのバランスを取っています。改正された規則に合わせてビジネスプロセスを調整することを治験依頼者に推奨します。」(訳注:この情報が掲載されたウェブページは、現在削除されています) 詳細な情報がEMAから近日中に発表されることが予想され、臨床試験用の新たなEU公共ポータル(Policy 0070)も同時に発表される可能性があります。改正CTIS透明性規則と重要な関連情報の概要については、EMA ACT EU公式サイトの「Implementation of the Clinical Trials Regulation」(CTRの実施)で確認できます。
3. EUの規制
EUイノベーション・ネットワークはACT EUと共同で、無料のウェビナー「Simultaneous National Scientific Advice (SNSA)」(全欧同時科学的助言)を2024年4月19日に開催します。本ウェビナーではSNSAの試験的導入について深く掘り下げ、SNSAの利点を理解し、新薬の開発プロセスの効率化について学ぶことができます。対象は大手製薬企業、中小企業(SME)、アカデミアなどです。本ウェビナーはライブ配信された後、録画ビデオが60日以内に公開される予定です。事前の質問は、Slido経由で4月12日まで受け付けています。
訳注1)ACT EU(Accelerating Clinical Trials in the EU):欧州での臨床試験の開始・設計・実施方法を革新して、高品質で有効・安全な医薬品の開発を促進することや、臨床研究を医療制度へさらに組み込むことなどを目的として、欧州委員会とEMAとHMAの三者が共同で開始したイニチアチブ。
訳注2)SNSA (Simultaneous National Scientific Advice):欧州の複数の国の各規制当局に、医薬品開発者が同時に科学的助言を求めることを可能にする制度。現在は試験的導入の第2期(phase 2)。
4. 英国とMHRAのニュース
4.1 英国のEU離脱後、2022年5月にMHRAはICHの正会員となりましたが、現在MRHAが適用中のICHガイドラインのリスト「Directory of current ICH Guidelines which have been implemented by the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency」が公開されました。本リストは、MHRAが新たなICHガイドラインを適用すると更新されます。
4.2 英国国民保健サービス(NHS)医療研究機構(HRA)の公式サイトの「Make it Public campaign」ページでは、2024年3月に開催された「Make it Public week」(研究開示啓発週間)のハイライトが紹介されています。「Make it Public」キャンペーンは、研究をすべての人に対してオープンでアクセス可能なものにするための啓蒙活動で、臨床試験登録率100%の実現を目指しています。
5. 欧州EMAのガイダンスとニュース
HMAとEMAは「HMA/EMA draft guidance document on the identification of personal data and commercially confidential information within the structure of the marketing authorisation application (MAA) dossier」(医薬品販売承認申請 [MAA] 書類中の個人情報と商業機密情報 [CCI] の特定に関するガイダンス文書案)を発表しました。2024年4月12日から6月28日までこちらでパブリックコメントを募集しています。
6. リアルワールドデータ
6.1 PHUSEリアルワールドエビデンス(RWE)・ワーキンググループのプロジェクト「Best Data Practices for Rare Disease Patient Foundations and Researchers」(希少疾患の患者団体と研究者のためのベスト・データ・プラクティス)は、新たにポスター「Ensuring Registry Data Relevance and Reliability for Regulatory Use」(規制当局が使用するレジストリデータの妥当性と信頼性の確保)を発表しました。本ポスターの内容は、(1)データガバナンスとデータインテグリティ(完全性)、(2)目的に適したデータ、(3)セキュリティとプライバシーの3点です。
訳注)PHUSE:Pharmaceutical Users Software Exchange。製薬企業やIT企業などのデータマネージメントや生物統計、電子臨床データ、毒性、病理、薬理などの各専門家ボランティアから成る国際的非営利組織。FDAやEMA、CDISCなどの規制当局・機関に対する業界代弁者。
6.2 DARWIN EU(Data Analysis and Real-World Interrogation Network:データ分析・リアルワールド質問ネットワーク)は、RWE生成のためのデータパートナーを今年新たに10件募集しています。DARWIN EUが患者のためにRWDをどのように利活用しているかについては、ファクトシート「2 Years of Experience, DARWIN EU: Making health data count」(DARWIN EU、過去2年間の実績:医療データの価値向上)をご覧下さい。
訳注)DARWIN EU:EU全域のリアルワールド医療データベースから、ヒト用医薬品・ワクチンの使用、安全性、有効性に関して信頼性が高くタイムリーなエビデンスを、EMAとEU加盟国の規制当局に提供するために、EMAと欧州医薬品規制ネットワークが2021年に設立した組織。
6.3 EMAは「Guidance on real-world evidence provided by EMA: Support for regulatory decision-making」(EMAが提供するRWEに関するガイダンス:規制上の意思決定支援)を発表しました。本ガイダンスは、(1)RWDの分析から得られるRWEが、規制上の意思決定にどのように役立つか、(2)実施可能な研究の種類、(3)研究課題の解決に最適なリソースを見極めるためにEMAがどのように支援できるかの3点について概説しています。
7. 透明性・情報開示のリソースとニュース
7.1 PHUSEのデータ透明性ワーキンググループ内のEU CTR実装プロジェクトは、EU CTR実装に関して最新ブログ「EU CTR Update: Year 2」(EU CTRの最新情報:実装2年目)を発表しました。このブログは臨床試験の透明性に焦点を当て、治験依頼者の観点からCTR実装2年目の実績を概説しています。
7.2 TransCelerate社はウェビナー「Enabling Individual Participant Data Return (iPDR): An Overview of TransCelerate’s Individual Participant Data Return Package」(個別被験者データ返却(iPDR)の実現:TransCelerate社の個別被験者データ返却パッケージの概要)のスライドとビデオ録画を公開しました。臨床試験の被験者に提供する被験者本人の治験データには、下記の情報などが含まれます。
- 臨床試験の全期間中(登録期間・スクリーニング期間を含む)に被験者から得られた個人レベルの被験者データ(医療健康データなど)
- 治験プロトコルや評価・活動スケジュールに規定された試験方法で得られた被験者個別情報と検査結果(ただし、試験結果を構成しないもの)
- 臨床試験中に被験者の検体から得られた被験者個別情報と検査結果
7.3 El Emamらはオープンアクセス論文「An evaluation of the replicability of analyses using synthetic health data」(合成医療データを用いた分析の再現性の評価)を発表しました。本論文は、医療データの共有を目的としたプライバシー保護技術としての合成データ生成の利用について解説し、その再現可能性を検証しています。
8. 開発戦略ニュース
8.1 Allucent社のブログ記事「Best Practices in Clinical Study Protocol Writing」(治験実施計画書の最も効果的なライティング)は、治験プロトコル作成へのアプローチの仕方の概要・ガイドを示しています。主なポイントは、(1)自分の担当範囲を把握すること、(2)試験のアウトライン(概要)を、活動(試験関連イベント)のスケジュールとともに早期に作成すること、(3)試験の目的とエンドポイントを明確に決めること、(4)プロトコルの利用者(治験責任医師、治験実施施設のスタッフ、規制当局、試験担当者など)を念頭に置いて、内容を構成・執筆することなどです。
8.2 Allucent社のウェビナー「Sample Size Re-Estimation: Risk Mitigation at the Planning Stage」(サンプルサイズの再推定:計画段階におけるリスク軽減)のビデオ録画は、臨床試験のサンプルサイズ設計戦略の全体像を詳しく説明しています。(十分な検出力やpatient enrichmentなどを目的として)サンプルサイズ再推定の実施が一般的になりつつある中、再推定の意味を理解することは、プロトコル作成に携わる全ての関係者にとって有益です。本ウェビナーでは、サンプルサイズ再推定のタイプ、盲検下の再推定と非盲検下の再推定の違い、オペレーション上と規制上の留意点について解説しています。
8.3 Nguyenらの総説論文「Regulatory Issues of Platform Trials: Learnings from EU-PEARL」(プラットフォーム試験の規制上の問題:EU-PEARLからの学び)は、プラットフォーム試験のマスタープロトコル作成時の留意点に関して最新の評価を提示しています。主な論点は試験デザイン(例:多重比較のための多重性調整)、申請時の留意点、規制当局とのコミュニケーション、医療技術評価(HTA:health technology assessment)、統計上の課題などです。また、本論文は、CTIS(EU-CTR)に提出された最初のプラットフォーム試験の1つであるEU-SolidAct試験の事例を簡単に紹介しています。
訳注)EU-PEARL(EU-Patient Centric Clinical Trial Platforms):患者中心で効率的な臨床試験を目指し、Innovative Medicines Initiative(IMI)から資金提供を受けて2019年に開始された官民共同プロジェクト。患者や医師、研究者、規制当局、産業界を各々代表する36組織が協力して、欧州における患者中心のプラットフォーム試験の設計や実施を支援するツールなどを開発。
 翻訳:内山 雪枝(クリノス 代表)
翻訳:内山 雪枝(クリノス 代表)
元医師、医学翻訳者、メディカルライター、セミナー講師。
明の星女子短期大学英語科卒業。東海大学医学部卒業。
大学病院勤務後、国内翻訳学校と米国大学院で翻訳を学び、
医学翻訳を30年以上手掛ける。
英文メディカルライティングの教育活動も20年以上継続中。
所属団体:米国メディカルライター協会(AMWA)(1996年~現在)
著書:『薬事・申請における英文メディカルライティング入門』I~IV巻(完売)
→ 詳しいプロフィールはこちら