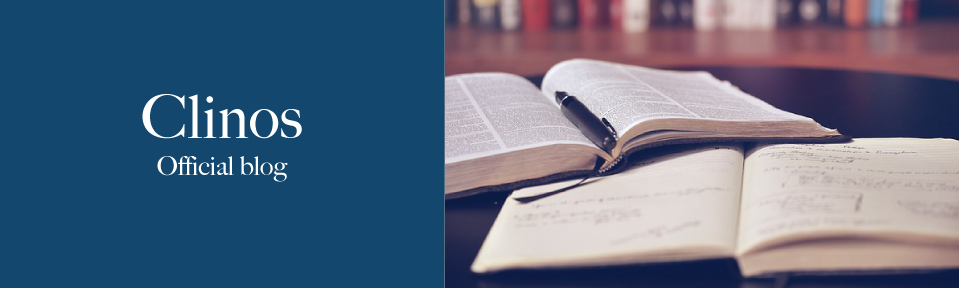著作者:pohjakroon、出典:pixabay
論文掲載料の搾取を目的とした「ハゲタカジャーナル」や、学会参加費の搾取を目的とした「ハゲタカ学会」といった詐欺商法は、日本でもよく知られ、警戒が広がりつつありますが、「ハゲタカアワード」はご存知でしょうか。日本ではまだあまり知られていませんが、海外では広く知られている詐欺の一種で、実際に多くの個人や企業が被害に遭っています。
最近、筆者にも偽アワードの授賞通知が届きましたので、本記事ではその実例を紹介しつつ、「ハゲタカアワード」の手口や特徴などを詳しく解説し、被害を未然に防ぐための対策をお伝えします。
1. ハゲタカアワードとは
ハゲタカアワードとは、偽の授賞組織(predatory award organization)が架空の賞を作り、もっともらしい授賞通知を個人や企業などに送り付け、受賞料などの名目で金銭をだまし取ろうとする詐欺です。
英語では「vanity award」(虚栄賞)、「fake award」(偽の賞)、「predatory award」(ハゲタカアワード)などと呼ばれています。「vanity」の意味「虚栄心、虚飾、見せかけだけで実質的に無価値・無意味」が示す通り、ハゲタカアワードに権威や価値、意味などは全くありません。お金さえ払えば誰でも「受賞」できます。いわゆる「お金で買える賞」です。
ハゲタカアワードの種類としては、学術界を狙った偽の科学アワード(例:Asia Research Awards)や、ビジネス業界を狙った偽のビジネスアワードなど、様々なものがあります。
ターゲットとしては、ある程度の実績があり、名前が世に出始めた個人や企業などが狙われる傾向があります。例えば偽の科学アワードのターゲットは論文発表経験のある若手医師・研究者、偽のビジネスアワードのターゲットは小規模事業者(スタートアップ企業、ベンチャー企業、個人事業主・フリーランスなど)が中心です。
偽の授賞通知の送付には、論文のcorresponding author(責任著者)の連絡先や、事業者の問い合わせ先、学会・専門家団体の名簿などが悪用されています。
2. ハゲタカアワードの実例:『Life Sciences Review』誌の偽アワード
(1)『Life Sciences Review』誌からの授賞通知
実際に筆者にも偽アワードの授賞通知が最近届きました。差出人は『Life Sciences Review』誌のFelicia Nelsonと名乗る人物で、「アジア太平洋地域の2025年トップ治験翻訳会社の最終選考に貴社がノミネートされました」という英文メールでした。
受賞にあたっては3000ドル(約45万円)支払う必要があり、その対価として『Life Sciences Review』誌での受賞者紹介、紹介記事の二次利用、賞状、受賞ロゴなどが含まれる、いわゆる「受賞パッケージ」が提供されるとのことです。ご参考までに授賞通知の全文をお示しします。
——————————————————————-
送信者:Felicia Nelson(felicia.nelson@thelifesciencesreview.com)
件名:Top Clinical Trial Translation Service recognition for Clinos by Life Sciences Review
I am Felicia from Life Sciences Review APAC, a premier print and digital magazine reaching over 86,000 qualified subscribers. Renowned for spotlighting advancements and industry leaders, our magazine connects lifesciences innovators with key decision-makers across pharmaceuticals, biotech, and healthcare sectors.
I am excited to share that we have shortlisted Clinos to be featured as the ‘Top Clinical Trial Translation Service in APAC 2025’ in our upcoming edition. We have shortlisted you based on nominations from our subscribers and a comprehensive evaluation by experts panel and editorial team. This prestigious recognition highlights your exceptional repute and the credibility you’ve cultivated among your customers and peers.
As the SOLE company to receive this recognition, we are proffering you the reprint rights to help maximize its impact.
To commence with this recognition, we want to feature an engaging profile about you, highlighting what makes you unique in the industry among hundreds of other companies. It will give insightful, real-world examples of your services to readers/prospective clients so they can better relate to how beneficial it will be for them to partner with you. The intent is to tell an engaging story of what you bring to the table and how that’s different from others.
Alongside your company’s engaging profile, we will feature articles from decision-makers who manage R&D projects, oversee clinical trials, or handle strategic partnerships within their organizations. They will share their insights on the key challenges and innovations shaping the lifescience sector, positioning your company prominently in front of influential decision-makers.
Being recognized as a top company in our magazine has empowered our clients in the lifesciences sector to increase visibility significantly. Furthermore, They have leveraged their recognition reprints to expand their client base. Clinos can receive similar impactful results by using the reprints strategically in its outreach efforts. This recognition as the ‘Top Clinical Trial Translation Service in APAC’ from an esteemed magazine will add credibility to your services, assuring prospects of your leadership and excellence in the lifesciences sector.
Along with recognition’s reprint rights, your company will receive a certificate, a specialized ‘Top Clinical Trial Translation Service in APAC 2025’ logo, and more benefits, all for 3000 USD. Clinos’s profile will also be featured on our website, hyperlinked to your website, where all its potential clients can directly reach your company for business inquiries.
Your company’s profile will receive significant exposure in front of our magazine’s large and relevant audience actively looking for a dependable partner comprising senior decision-makers working in Pharmaceuticals, Biotechnology, Healthcare IT, Medical Device Manufacturing, and other companies.
I would like to connect and discuss how your company can leverage this recognition to increase its visibility, just like our previous clients. Let me know the best time to schedule the conversation.
Regards,
Felicia
______________
Felicia Nelson
Life Sciences Review APAC
O: +1 510 570 3495
——————————————————————
(2)授賞通知の違和感
この授賞通知メールを読んで、すぐに「おかしい」と感じた点が3つありました。
①的外れなアワード:通知には「治験翻訳サービスでノミネート」と記載されていますが、当方は近年、治験翻訳を手掛けておらず、現在は主に英語論文の作成・投稿支援に注力しています。このような状況で、当方が「治験翻訳」のカテゴリーでノミネートされたという点に、まず不自然さを感じました。
②非現実的な審査:治験文書の多くは機密情報であり、通常は第三者が自由に閲覧できるものではありません。また、治験文書の翻訳を担当した企業や個人の名前が開示されることもまずありません。そのため、「弊誌読者からの推薦や専門家・編集者らによる総合的な評価に基づいて貴社をノミネートした」という説明に、疑念を抱きました。
③受賞費用の請求:当方はこのアワードに応募した覚えは一切ありません。それにもかかわらず、「ノミネートされた」と一方的に通知され、さらには受賞費用の支払いが必要という点に強い違和感を覚えました。正当なアワードでは、受賞者が金銭を支払わなければならないケースはまれです。
(3)『Life Sciences Review』誌の不審な点
このような違和感を覚えたため、『Life Sciences Review』誌のウェブサイトとSNSを探し、同誌とアワードの実態について調べました。いずれも一見それらしく見えるものの、以下のような不審な点が次々と見つかりました。
- 企業情報の不足:所在地として「米国フロリダ州フォートローダーデール」と記載され、メールアドレスが示されているだけで、社名や住所、電話番号、代表者など、企業サイトにあるべき基本情報が見当たりません。
- 編集体制の不明瞭さ:編集長、編集委員、発行頻度、購読料、バックナンバーといった、雑誌としての情報が全く公開されていません。
- コンテンツの偏り:サイトで公開されている記事の多くは「アワード受賞者の紹介」で、ライフサイエンスに関する専門記事や業界分析などはあまり見当たりません。
- 審査の不透明さ:アワードの審査員や選考基準、選考方法などの情報が一切公開されていません。
- 授賞対象分野の広さ:アワードの対象はライフサイエンスの特定の分野に絞られておらず、様々なライフサイエンス分野を対象にアワードが乱発されています。
- 授賞発表の多さ:SNSでは、毎月、多数の企業が「受賞者」として発表されており、このことからもアワードの乱発が伺えます。
- 公開情報の不整合:SNSとは対照的に、サイトに過去の「受賞者」として掲載されているのは、2種類のアワードの過去2年分のみに留まっています。また、「トップ10企業」が選出されているライフサイエンス分野のうち、10社すべてが公開されている分野はほとんど見当たりません。実際には、受賞料を支払った企業のみを発表して「受賞パッケージ」を授与している可能性が考えられます。
- 購読者数の疑わしさ:授賞通知メールでは「86,000人超の購読者がいる」と謳われています。しかし、同誌のLinkedInのフォロワーは2,400人程度で、購読者数との乖離が大きく、購読者数の信憑性に疑念を覚えます。
(4)ネット上の関連情報
「Life Sciences Review」をキーワードにしてネット検索を行ったところ、同誌からのアワード受賞を発表している企業の公式サイトが多数ヒットしました。このことからもアワードの乱発が裏付けられます。
また、X(旧ツイッター)上には、筆者に届いたものとほぼ同じ内容の授賞通知メールが全文掲載されている投稿があり、その投稿者は『Life Sciences Review』誌を「ハゲタカジャーナル」と呼んで警鐘を鳴らしています。このような投稿が複数確認できる点からも、同誌が同様の手口でアワード受賞への勧誘を繰り返している可能性が示唆されます。
(5)日本企業もターゲット
『Life Sciences Review』誌からのアワード受賞を自社の公式サイト・SNSで発表している企業の中には、日本のバイオベンチャー企業や、CRO(医薬品開発業務受託機関)、学術情報・論文作成支援企業なども確認されました。このことから、日本企業もすでに同誌のターゲットになっており、国内でも被害拡大の可能性が懸念されます。
(6)米国メディカルライティング業界内での認識
さらに筆者は米国メディカルライター協会(AMWA)の会員専用フォーラムで、『Life Sciences Review』誌からの授賞通知を共有し、同誌や類似の偽ビジネスアワードに関する情報提供を呼び掛けました。
すると、複数の会員から以下のようなコメントが寄せられました。
- 「こうした偽ビジネスアワード受賞の勧誘は非常に多く、よくある手口」
- 「私も数ヵ月前に同じようなメールを受け取った」
- 「騙されなかったようで良かったですね」
アメリカのメディカルライティング業界でも、偽ビジネスアワードが「詐欺」として広く認識されていることが確認されました。
(7)しつこいリマインダー
筆者はこれらの調査結果を踏まえ、『Life Sciences Review』誌のアワードは「ハゲタカアワード」であると判断し、授賞通知には一切返信せず削除しました。
しかし、その後も同誌のNelson氏からリマインドメールが複数回届いており、「しつこい勧誘」が続いています。これもハゲタカアワードによく見られる特徴の1つです。実際、あるAMWA会員は、別の偽の授賞組織から受賞勧誘メールが「数ヶ月間に20回以上届いた」とコメントしていました。
(8)実体は「広告媒体」
調査を重ねるうち、『Life Sciences Review』誌は、いわゆる学術誌や業界誌ではなく、受賞者の紹介を中心とした「広告雑誌」である可能性が高いことも判明しました。
同誌は受賞者の写真と紹介記事を掲載したファイルを作成し、それを「受賞パッケージ」として受賞者に提供(販売)し、写真と紹介記事をサイトに掲載するだけで、あたかも雑誌に取り上げられたように演出している印象を受けます。
筆者に届いた授賞通知メールでは「a premier print and digital magazine」と謳われていますが、雑誌としての発行実態は確認できず、いわば「受賞者専用の販促ツール」に過ぎないと思われます。
AMWA会員からも本質を突いたコメントが寄せられました。
- 「3000ドル払えば受賞パッケージを自分のビジネスの宣伝に使えるというだけで、基本的には広告だ」
- 「多くの偽ビジネスアワードは、何かを受賞したように見せかける広告パッケージか詐欺(scam)。お金さえ払えば個人や企業を掲載してくれる広告媒体に過ぎない」
こうした指摘からも、『Life Sciences Review』誌が提供するアワードは「栄誉」ではなく、「広告スペースの販売」を目的とした商業的な詐欺スキームであると考えられます。
3. ハゲタカアワードから身を守る方法
ハゲタカアワードは、見かけ上は「権威ある賞」を装いながら、実際には受賞料などを搾取するだけの「偽アワード」です。まずは、このような詐欺的アワードの存在を認識することが防御の第一歩です。
もし思いがけない授賞通知が届いたら、「疑う、調べる、相談する」の3ステップで冷静に対応することを心掛けましょう。以下の8つのポイントを確認することで、被害や誤認を防ぎやすくなります。
(1)授賞通知を冷静に読み、内容を正確に理解する
研究や仕事が評価されたという知らせは嬉しいものですが、すぐに返信するのは禁物です。文面を落ち着いて読み、アワードの趣旨や対象、記載内容の具体性や妥当性などを確認しましょう。
(2)不審なメールのリンクは絶対にクリックしない
授賞通知を装ったメールには、ウイルス感染や個人情報搾取を狙うリンクが含まれている場合があります。特に授賞通知に不自然な英文や見慣れないドメインのURLがある場合は、リンクをクリックせずにメールを削除しましょう。
(3)金銭を要求されたら詐欺を疑う
正当なアワードであれば、「受賞料」などの名目で追加の費用を請求することはまずありません。エントリーもしていないのに授賞通知が届いたり、「受賞パッケージ」などの購入を求められたりした場合は、ハゲタカアワードの典型的な手口と考えてよいでしょう。
なお、初回の通知では料金が明記されず、後日メールやウェブサイトで費用が提示されるケースもあります。最初に金銭の記載がないからといって、安心するのは早計です。
(4)授賞組織の実態をサイトとSNSで入念に調べる
- 公式サイトやSNSは整備されているか、不自然な英語や日本語はないか
- 名称、住所、電話番号、代表者などの基本情報が明記されているか
- アワードの趣旨や実績などが具体的に紹介されているか
- 授賞式は開催されているか、開催時期、場所、出席者などは妥当か
- 受賞費用に関する記載はないか、高額ではないか
(5)過去の受賞者情報を確認する
- 受賞者の氏名・所属先が公開されているか、実在するか
- 受賞者数が極端に多すぎたり、少なかったりしないか
- アワードの内容と受賞者の専門性が一致しているか
(6)審査体制を確認する
- 審査委員会は設置されているか
- 審査員は公開されているか、実在するか、しかるべき専門家か
- 選考基準や選考手順が具体的に示されているか
(7)ハゲタカアワードのリストを参照する
過去に報告されたハゲタカアワードや疑わしいアワードの一覧も参考になります。
- オランダのライデン大学医療センターのEsther van de Vosse准教授によるブログ「Predatory award organization – yet another scam」(英語)では、偽の科学アワードがリストアップされています。
- ハゲタカジャーナル・学会を扱う専門サイトで、偽アワードの関連情報が紹介されていることもあります。
(8)1人で判断せず、周囲に相談する
授賞通知に少しでも疑問を感じたら、同僚や上司、信頼できる業界関係者に相談しましょう。授賞通知と調査結果を共有し、複数の人の視点で慎重に判断・対応することが、最終的な被害防止につながります。
4. ハゲタカアワードの被害防止に協力を
ハゲタカアワードは、受賞者にとっては一見「名誉」のように見えますが、実際には受賞料などの名目で金銭を奪い取る巧妙な詐欺です。知らずに関わってしまうと、研究者や企業などの信用を損なうリスクもあります。
こうした被害を未然に防ぐために、本記事の内容をご同僚やご友人、業界関係者の方々と共有していただけますと幸いです。SNSでのシェアや、メール・社内チャットなどでのご紹介も大歓迎です。1人でも多くの方に「ハゲタカアワード」の存在や手口、特徴を知っていただければ、それだけで大きな防波堤になります。
また、『Life Sciences Review』誌などによる偽アワードの受賞を公表している方や企業・研究機関をご存じでしたら、ハゲタカアワードの可能性をそっと教えて差し上げてください。ご本人たちは悪意なく受賞を喜んでいる可能性が高く、第三者からの指摘で初めて詐欺に気づけるケースも少なくありません。
ハゲタカアワードによる被害を受けた方や企業・研究機関は、互いに連携して複数で詐欺組織に立ち向かうことで、被害の回復やその後の再発防止につながりやすくなります。
ハゲタカアワードの情報を広く共有し、被害の連鎖を断ち切ることは、私たち専門職の信頼を守る大切な一歩です。何卒ご協力をお願いいたします。
5. ハゲタカアワードのまとめ
- 受賞料などの搾取を目的とした詐欺
- 名誉に見えて、実は「お金で買う賞」または「広告媒体」
- 存在を知り、手口や特徴を理解することが対策の第一歩
- 授賞通知が届いたら「疑う、調べる、相談する」の3ステップで冷静に対応
- 不審な授賞通知には返信せず、毅然と無視
- 受賞を公表すると、かえって信頼失墜の恐れあり
- 情報を広く共有し、被害の拡大を防ぎましょう
【2025年8月29日追記】偽授賞通知が再び届いた!
最近、『Life Sciences Review』誌から偽の授賞通知メールが再び数回届きました。今回は差出人が「Katherine Phillips」に代わり、送信元のドメインも「lifesciencesreviewapac.com」に変更されていましたが、内容は前回(2025年春)の偽授賞通知と全く同じで、3000ドルの「受賞料」を請求するものでした。通年で何度も同じアワードの授賞通知が送られてくる点からも、やはり同誌のアワードの信頼性は低いと言えます。
偽の授賞通知の再送を受け、改めて「Life Sciences Review」でネット検索を実施したところ、新たに日本国内の医薬翻訳会社が『Life Sciences Review』誌からの受賞を本年6月に自社サイトで発表していることが確認されました。同誌のハゲタカアワードの被害が国内でもじわじわ広がっているようですので、授賞通知が届いても安易に信じてしまわないよう、「疑う・調べる・相談する」の3ステップで冷静に対応なさって下さい。

著者:内山 雪枝(クリノス 代表)
元医師、医学翻訳者、メディカルライター、セミナー講師。
明の星女子短期大学英語科卒業。東海大学医学部卒業。
大学病院勤務後、国内翻訳学校と米国大学院で翻訳を学び、
医学翻訳を30年以上手掛ける。
英文メディカルライティングの教育活動も20年以上継続中。
所属団体:米国メディカルライター協会(AMWA)(1996年~現在)
著書:『薬事・申請における英文メディカルライティング入門』I~IV巻(完売)
→ 詳しいプロフィールはこちら
※メールマガジン「クリノス通信」(無料)
国内外の業界情報や、英文ライティングのワンポイントレッスンなど
医薬翻訳・メディカルライティングに役立つ情報をお届けしています。
→ 購読申込はこちら