昨年(2016年)も米国メディカルライター協会(AMWA)年次総会に参加して来ましたので、遅ればせながら報告いたします。2016年の総会は10月5~8日にコロラド州デンバーで開催され、名称が「annual conference」から「Medical Writing & Communication Conference」に変わりました。
日本からの参加者は今年も約15名で、大部分は国内製薬企業のメディカルライターの方でしたが、フリーランスのライターや医薬翻訳者の方も数名いらっしゃいました。参加者名簿を見る限り、国内のアカデミアやCRO、翻訳会社からの参加はなかったようです。
会期中には、毎年恒例の日本人参加者の夕食会を開催しました。医薬分野の英訳を手掛けるネイティブ翻訳者の方も数名参加して下さり、医学英語の勉強法からアメリカ大統領選まで幅広い話題で盛り上がり、今回も楽しく有意義な時間を過ごすことができました。
 AMWAオープン・セッションで個人的に最も期待していたのは、2015年同様、治験総括報告書(CSR)の作成マニュアル「CORE Reference」の説明会で、今回も多くの参加者が集まり盛況でした。欧州メディカルライター協会(EMWA)とAMWAが共同で「CORE Reference」を作成した経緯などは、本ブログの第15回「製薬業界のメディカルライター必見!EMWAとAMWAがCSRマニュアル『CORE Reference』を共同作成中」にまとめてありますので、背景を知りたい方はそちらをご覧頂きたいと思いますが、ついに2016年5月に「CORE Reference」がネット上で公開され、利用が始まりました(「CORE Reference」公式サイト)。
AMWAオープン・セッションで個人的に最も期待していたのは、2015年同様、治験総括報告書(CSR)の作成マニュアル「CORE Reference」の説明会で、今回も多くの参加者が集まり盛況でした。欧州メディカルライター協会(EMWA)とAMWAが共同で「CORE Reference」を作成した経緯などは、本ブログの第15回「製薬業界のメディカルライター必見!EMWAとAMWAがCSRマニュアル『CORE Reference』を共同作成中」にまとめてありますので、背景を知りたい方はそちらをご覧頂きたいと思いますが、ついに2016年5月に「CORE Reference」がネット上で公開され、利用が始まりました(「CORE Reference」公式サイト)。
CSRの作成に関しては、ご存知のとおり「ICH E3ガイドライン」という国際的な指針があり、製薬企業はこのガイドラインに基づきながら、各々工夫を凝らしてCSRを長年作成しているので、すでに作成方針やテンプレートなどが確立されている企業が多いと思います。そのため、「CORE Reference」公開前から「何を今さら・・・」という疑問の声も聞かれます。
「CSRのマニュアルなど新たに必要ない」と考える製薬企業が多いかもしれませんが、AMWAのオープン・セッションでの説明を聞き、「CORE Reference」を読む限り、「CORE Reference」はICH E3ガイドラインに基づいているだけでなく、欧米の規制当局の最近のガイダンスも考慮して作成されているので、「CORE Reference」を利用すると海外の規制を遵守しやすくなると思います。また、「CORE Reference」は申請のためだけではなく、臨床試験データの公開も視野に入れて作成されているようです。
ご存知のとおりヨーロッパの規制当局(EMA)が新薬の臨床試験データの公開を義務付けたことから、薬剤の開発国・地域に関わらず、ヨーロッパで申請するすべての医薬品の臨床試験データを誰でも見られるようになりました。つまり、アメリカやアジアなどで書かれた臨床試験データもEMAを通じて公開されるということです。このような状況を踏まえ、いかにCSRに手を加えずにそのまま公開できるかということにも、「CORE Reference」は配慮して作られている印象を受けます。
そのため、「CORE Reference」のオープン・セッションでは、臨床試験データの公開時に規制当局が求める「透明性」(transparency)や「データの利用しやすさ」(data utility)と、被験者・開発側の個人情報(protected personal data [PPD])や医薬品の機密情報(commercially confident information [CCI])の保護とを、どのように両立させるかという説明に多くの時間が割かれていました。
別のオープン・セッション「Public Access to Clinical Documents — The New Transparency Policies in Europe」でも、「PPD」と「CCI」という略語が頻繁に使われ、これらの詳しい内容や保護方法に関する説明がありました。臨床試験データの公開におけるキーワードとして、この2つの用語は覚えておいたほうが良さそうです。
なお、「CORE Reference」は規制やガイドラインではないので、強制力はありません。また、CSRのテンプレートでもありません。欧米の各メディカルライター協会の会員で医薬品の申請資料作成に携わるメディカルライター(regulatory writer)らが意見をまとめた提案に過ぎません。作成に際しては日米欧3極とカナダの規制当局に相談したそうですが、関与を公式に表明しているのはカナダ当局のみです。また、欧米での利用度や普及範囲は、しばらく様子を見ないとわからないのが現状です。
しかし、「CORE Reference」は一読の価値があると思います。その理由は主に3つあります。
- 欧米のベテランの製薬専門ライターらの知識や経験などが色濃く反映されているので、欧米のCSR作成の考え方などを窺い知ることができる上に、ICH E3ガイドラインの欠点を補う形で作られているので、CSR改善のヒントが得られます。
- 臨床試験データの公開にCSRを利用する際に注意すべき点や、公開を前提に効率よくCSRを作成するコツなどがわかります。
- 欧米のベテランの製薬専門ライターらが質の高い英語で書いているので、正確かつ適切な英語表現を知ることができ、CSRの英文ライティングや和文英訳の参考になります。
このような利点がありますので、CSRの作成・翻訳に携わる方は、「CORE Reference」の利用の有無に関わらず、お手すきの折にでも一度ご覧になってみて下さい。公式サイトからどなたでも無料でダウンロードできます。また、メーリングリストに申し込むと、関連する最新情報が「CORE Rerference email」として随時無料で届くので、公式サイトから申し込んでおくと便利だと思います(申込ページはこちら)。
臨床試験データ公開のキーワード
・protected personal data (PPD)
・commercially confident information (CCI)
追記1:クリノス代表・内山雪枝が「CORE Reference」に送ったメールの一部が、「CORE Reference」公式サイトの「Adoption and Use」(利用者の声)に掲載されました。興味のある方はこちらをご覧下さい。
追記2:2018年7月にクリノスは、「CORE Reference email」の和訳とその配信に関する許諾を「CORE Reference」より取得しました。詳しいことはこちらをご覧下さい。
関連サイト・記事
⇒CORE Reference公式サイト
⇒製薬業界のメディカルライター必見!EMWAとAMWAがCSRマニュアル『CORE Reference』を共同作成中
RECOMMEND こちらの記事も人気があります。
⇒ICH E3ガイドラインに基づく治験総括報告書作成・翻訳の注意点
⇒有害事象の叙述の自動作成と治験報告書の公開
⇒有害事象の叙述を英語で書く
⇒説明同意文書向けの平易な英語表現
⇒『AMA Manual of Style』の勉強法
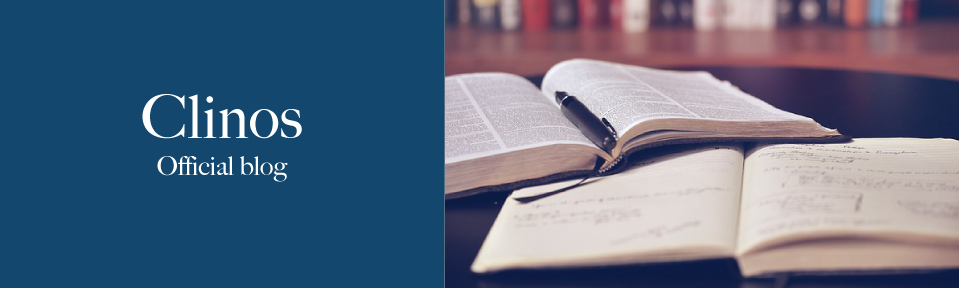



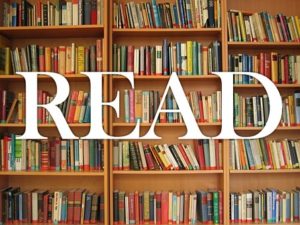
 著者:内山 雪枝(クリノス 代表)
著者:内山 雪枝(クリノス 代表)











 皆様の中にも命名法をご存知ない方がいるかもしれませんので、少しだけご紹介しましょう。例えば分子標的薬が何らかの阻害剤(例:チロシンキナーゼ阻害剤)の場合は、「△△ニブ(-nib)」と名付けます(例:ゲフィチニブ)。「-nib」は「inhibitor」の略です。一方、「抗体医薬」の場合は「△△マブ(-mab)」と名付けます(例:リツキシマブ)。「-mab」は「monoclonal antibody」(モノクローナル抗体)の略です。したがって、一般名の語尾を見れば、分子標的薬の種類がわかります。
皆様の中にも命名法をご存知ない方がいるかもしれませんので、少しだけご紹介しましょう。例えば分子標的薬が何らかの阻害剤(例:チロシンキナーゼ阻害剤)の場合は、「△△ニブ(-nib)」と名付けます(例:ゲフィチニブ)。「-nib」は「inhibitor」の略です。一方、「抗体医薬」の場合は「△△マブ(-mab)」と名付けます(例:リツキシマブ)。「-mab」は「monoclonal antibody」(モノクローナル抗体)の略です。したがって、一般名の語尾を見れば、分子標的薬の種類がわかります。 例えば「electrocardiography」という単語を見てみましょう。接頭語「electro-」は「電気の」という意味で、「cardio-」は「心臓の」という意味、そして接尾語「-graphy」は「検査(法)」という意味なので、これらを組み合わせて「心電図検査」という意味だとわかります。
例えば「electrocardiography」という単語を見てみましょう。接頭語「electro-」は「電気の」という意味で、「cardio-」は「心臓の」という意味、そして接尾語「-graphy」は「検査(法)」という意味なので、これらを組み合わせて「心電図検査」という意味だとわかります。
 したがって、プリンスさんが長年傷めていたのは「腰」ではなく「股関節」だったのです。「hip surgery」を「hip replacement」(=人工股関節置換術)と具体的に記載している海外の報道もありますので、「hip」は「股関節」で間違いないでしょう。「腰」と「股関節」では、部位がだいぶ違いますね。このような誤訳はプリンスさんの記事では大きな影響はないかもしれませんが、医学論文や製薬関連文書などで身体の部位を訳し間違えると、
したがって、プリンスさんが長年傷めていたのは「腰」ではなく「股関節」だったのです。「hip surgery」を「hip replacement」(=人工股関節置換術)と具体的に記載している海外の報道もありますので、「hip」は「股関節」で間違いないでしょう。「腰」と「股関節」では、部位がだいぶ違いますね。このような誤訳はプリンスさんの記事では大きな影響はないかもしれませんが、医学論文や製薬関連文書などで身体の部位を訳し間違えると、


